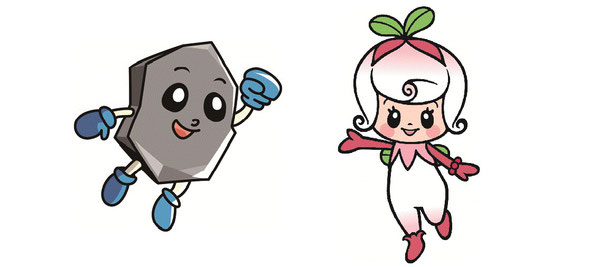上湧別村誌〈大正9年4月5日刊)より 「薄荷栽培の起源」について
薄荷は北見地方特産の農産物で、全世界生産額の1/2を占めている。
事の始まりは、明治28年、福島県人の渡部精司が藻瞥村より湧別村西1線7番地に移り住み、サロマ湖畔に生えていた野生の薄荷を見つけ、その茎を採取し乾燥して、郷里の福島県会津若松市に送り、含油量の試験をさせたところ、一貫目(3.75キログラム)に対し、3匁6分(3.75グラム×3.6=13.5グラム)の製油がとれたので、湧別地方の作付けもできるかもしれないと考え、育てるのに適した良い苗づくりをしようとしたが、当時は未墾状態の地であり、住む人もほとんどなく、交通の便は大変悪かったため、苗となる根を手に入れることはできなかった。
後に、北海道庁と札幌農学校に苗根の供給を何度となく照会した。たまたま農学校の助教授、鈴木武良氏とその生徒、眞鍛氏から石狩上川方面で栽培しているとのことを聞き、早速上川郡永山村(旭川市永山町)に行き、当時の植松戸長に尋ねたところ、山形県の移住者から種根一貫目25銭で6貫目を分けてもらった。中央道路(旭川―網走)を苦労して馬で運び、一畝(30坪)の畑に植えたのを最初とした。明治29年5月下旬であった。
この年の9月、乾燥させた茎は10余貫(40キログラム近く)を収穫し、簡単な蒸留法で製油したところ、93匁(3.75×93=350グラム)が得られたので、これはできそうだと思い、さらに製油の販路を求め、府県(東京を含め道外の県)に問い合わせたところ、東京の大木口哲氏からは1斤(600グラム)2円75銭、山形県北村上郡の某氏からは2円40銭または2円75銭で買い取るという回答を得た。
そこで、学田と4号線付近に住んでいる山形県人が薄荷栽培をしたことがあるというので試みさせようとしたが、種根が手に入らず、翌30年、高橋長四郎、有地護一、越田兼松の3人が相談して、上川郡永山村から一貫目15銭で150貫の種根を購入した。
大変な苦労をして湧別村に戻り、それぞれが5畝(150坪)の植え付けをしてみたが、輸送中に大部分の種根が腐ったり枯死したりしたので発芽が不良で、そのために有田、越田の2人は全部、植村の薄荷を高橋氏に譲った。
高橋氏は明治31年の秋になっても自分の畑で増やそうとしたが、もともとよく分かっていなかったこともあり、製法や販路についても見通せるかどうか分からず、どうしたらいいものか考えあぐねていた。
明治32年、学田の移住者で山形県人の佐竹宗五郎、小山田利七、小山田秀造氏らが高橋長四郎の薄荷栽培のことを聞き、高橋氏より一貫目20銭にて110貫目(400キロ以上)を購入し、字学田に移植した。この事が北見薄荷の今日(当時)の隆盛を迎えるもともとである。
同年、小山田利七氏は17斤(600グラム×17=10.2キロ)、秀造氏は12斤(7.2キロ)の油がとれた。これを郷里、山形県北村上郡小田島村の小野金太郎氏に送り、販売方法を委託したところ、一斤3円25銭で計97円50銭を得た。薄荷栽培が大変利益の上がることが近所の人たちにも知れ渡った。
翌明治33年、小山田利七氏は種根として一貫目20銭で10貫目を売り、残りは全て自分の畑に植えた。その広さは5反歩(300坪×5=1500坪)であった。
こうして収穫した薄荷油は、利七氏3反歩より36斤(21.6キロ)となった。これを小野氏に委託販売してもらったところ、一反あたり39円であった。これを聞いた人々は、利益の上がる作物だということで、種根を譲ってもらおうとした。しかし、もともとその量は少なく、需要を満たすことはできなかった。けれども、明治34年には生産量の増加とともに、横浜の薄荷輸出商、小林某氏自らが湧別村に来て、買い付けを行い一斤あたり3円20〜30銭の高値となった。
明治35年には、作付面積は昨年の2倍ほどに増やしたにも関わらず、10月上旬には一斤5円、同下旬には7円70銭で購入という高値になった。この年は平年作とは言え、村内栽培者が増えたことはもちろん、野付牛村(北見市)地方より種根購入の申し込みが殺到した。
明治36年には栽培面積、前年の倍、200町歩(200ha)以上となった。しかし油の取引価格はやや低く始まり、はじめは5円から5円20〜30銭の愛度を上下していた。最後には3円75銭までに下がってしまった。村内では主に4円50銭から5円までの間に売りさばいた。この年は紋別郡渚滑村から種根の購入者が来村したため、一貫目10銭から15銭で売ることができた。
明治40年には、作付面積は800町歩(800ha)になったが、病虫害に罹り収穫は減少、その上、油の価格が一斤2円40銭に低下したため大いに痛手だった。
明治43年にはさび病が発生し、再び多少の被害を受けたものの、その年は順調に生産が伸び、同時に各地から薄荷購入商人が入り込み、競って買い付けをした。
大正元年は一組(320斤=196キロ)15円余りの最高値となった。薄荷は毎年生産額も価格も変動するので農産物の中では安定しない危険なものであると思われたが、欧米各国や中国、東南アジアなどへの販路が拡大し、需要は大変多く、しかも品質で山形県や三備地方(岡山県広島県)の上をいく優良品を生産しているので、(この村誌ができた時点での)将来もまだまだ有望であることは間違いない。
近頃は、青エンドウ、小手芒豆、でんぷん粉などの価格が空前の高値などと買い入れ商人が少ないのをいいことに、生産者の生活の様子を窺い、その弱点に付けこみ、買い占めるような傾向がある。(収量は)一時減ったものの、大正6年の本村の総生産額は480,955組 118,065円であった。これは全農産物の23.9%を占めた。
薄荷商人として本村に入ってきたのは、横浜小林のほか明治37年以来の神戸ウェンケル商会、40年以来の横浜多勢、神戸の曲辰鈴木合名会社、44年以来の横浜長岡などであった。鈴木合名会社と小林は遠軽市街に各出張所を設けて、毎年、搾油期の10月以降に店員が出張し、買いつけていた。
今(この当時)薄荷栽培と普通作物栽培との一反歩に対する小作料を下記に対比する。
|
|
|
薄荷 |
普通 |
|
一等地 |
1 |
4円 |
5円 |
|
|
2 |
3円 |
4円20銭 |
|
|
3 |
2円 |
3円40銭 |
|
二等地 |
1 |
3円 |
4円40銭 |
|
|
2 |
2円 |
3円50銭 |
|
|
3 |
1円70銭 |
3円 |
|
三等地 |
1 |
2円 |
3円50銭 |
|
|
2 |
1円50銭 |
3円 |
|
|
3 |
1円20銭 |
2円80銭 |
|
新墾地 |
1 |
1円50銭 |
3円 |
|
|
2 |
1円 |
2円80銭 |
|
|
3 |
80銭 |
2円60銭 |